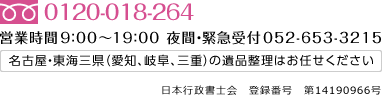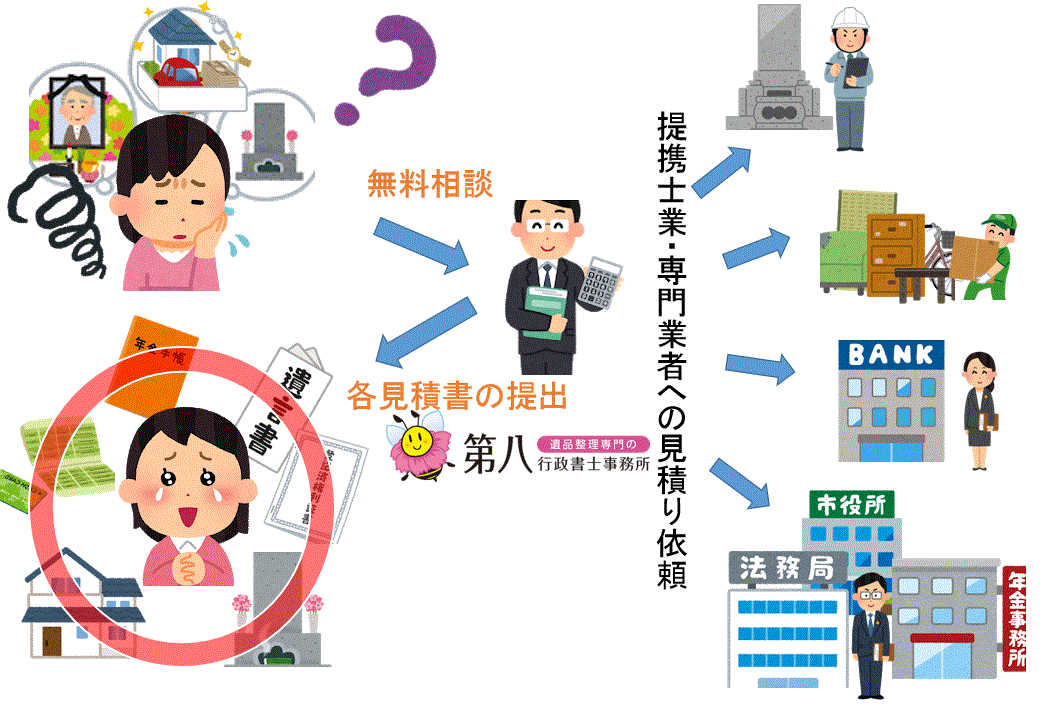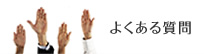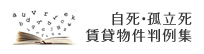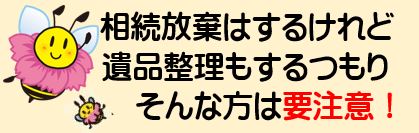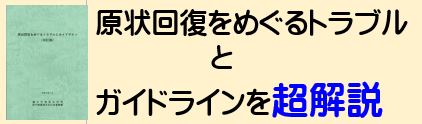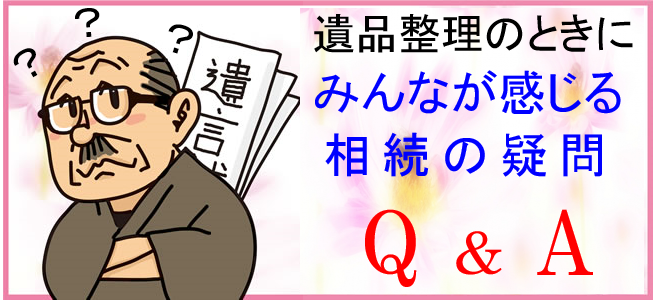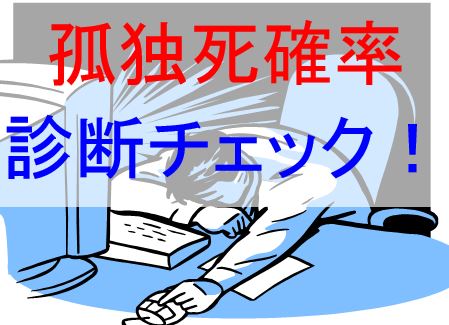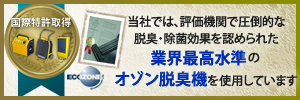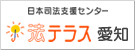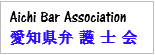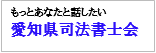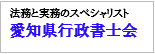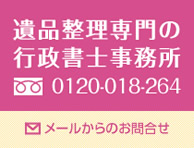名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2025.02.03
賃貸物件の緊急連絡先と死後事務受任者の役割
おはようございます。名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八行政書士事務所の谷です。
節分に恵方巻を食べるというのは最近では珍しくなくなってきましたが、私が最初に恵方巻を知ったのは20年近く前でしょうか。
当時はまだ恵方巻の由来も知らず、「縁起物の食べ物なのか」程度の認識で、当時勤めていた不動産会社に昼食代わりに買っていき、恵方巻を輪切りにして事務所のみんなで食べていました。
今なら恵方巻を切るなんて!となりそうですが、当時はその程度の認識の食べ物でしたが、いまでは節分の風物詩といっても良いくらい浸透していますよね。バレンタイン商戦に近い企業の戦略を感じます(笑)
さて、本日の話題は、賃貸契約における緊急連絡先と死後受任者の役割についてとなります。
近年は、民法の改正もあり賃貸契約における連帯保証人の役割は「保証会社」が担うことが多くなり、親族等は「緊急連絡先」として、賃貸契約書に記載されることがほとんどかと思います。
緊急連絡先としての役割は、基本的には本人に連絡がつかない際に代わりに連絡を受けてくれる人となります。緊急連絡先として登録されたとしても、連帯保証人のように延滞家賃を代わりに支払う義務などはありません。
ただ、事故や災害等が起きた際に入居者本人と連絡が取れない際に親などが緊急連絡先に指定されていれば本人の安否確認が取れるといったケースや、入居者の部屋から漏水が起きている場合に本人が仕事中で電話に出てくれない様な際に親元へ連絡して、管理会社が室内へ入る許可を貰ったり、場合によっては入居者本人が家賃を滞納している際などにも、本人と連絡を繋げてもらう意味で緊急連絡先に連絡が入るといったこともあります。
このように緊急連絡先は何かトラブルが生じた際にあくまで本人との連絡を繋いでもらうための役割を担うものとなりますが、では緊急連絡先には誰を指定すれば良いのか?となると、誰でも良いという訳にはいきません。
緊急連絡先の役割が本人との連絡の繋ぎ役ということでしたら、本人の連絡先を知っている方なら誰でも良いということになりますが、緊急連絡先に連絡が入るということは、何かしら「緊急の事態」が起きていることが前提となります。
つまり、その緊急事態、例えば「家賃の未納が続いているが本人と連絡が取れない」といった様な場合であれば、本人が今どういった状況に置かれているのかをある程度把握できている人でなければいけません。
家賃の滞納が続くケースとして考えられるのが、
① 本人の家賃引き落とし口座に残高が残っていなかった
② 入院している為、家賃の振込ができなかった
③ 長期出張や海外旅行に出ており、振込できなかった
④ 多重債務で夜逃げした
⑤ 室内で孤独死しており振込されなかった
等々、家賃滞納が発生する理由は色々ありますが、緊急連絡先となっている方が入居者の親御さんであれば、①~⑤のような事が起きれば、入居者本人へ連絡を取って家賃の振込を促したり、滞納になってしまった原因を管理会社に説明したり、入居者の安否確認のために室内の状況を確認してくれるといった対応を期待できます。
ただ、緊急連絡先となっている方が入居者本人の電話番号を知っているだけの友人のような場合でしたらどうでしょうか?
大家さんや管理会社が緊急連絡先として登録されている「友人」へと電話したとしても、その友人が本人の状況を何も把握していなければ管理会社等から連絡を受けても「はぁ、そうですか、でも私も何も知りません」で終わってしまう可能性もあります。
ですので、緊急連絡として登録される方には、連帯保証人のような義務を負わないまでも、ある程度本人の事に対して裁量権を持っている方が望ましいことになります。
そういった意味で、不動産会社や保証会社の担当者が緊急連絡先として親族の方しか認めないという可能性は出てきます。
ただ、高齢の入居者のような場合は、頼れる親族がいないという事も珍しくないため、親族しか緊急連絡先としては認めないとされてしまうと、ただでさえ単身高齢者の契約できる賃貸物件が少ない中、さらに選択肢が狭まってしまうことになります。
では、こうした状況下に置いて、死後事務受任者としてはどのような役割を担えるのでしょうか。
死後事務受任者の契約上の役割は、委任者(本人)が亡くなった場合における委任者の死後の手続について親族等に代わって行うことにあります。
また、死後事務委任契約の締結の際には、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言執行者への就任等、おひとり様が抱える問題を解決するために、複数の契約をしていることも珍しくはありません。
ですので、ひとりの死後事務受任者が、任意後見受任者や遺言執行者をもまとめて兼任している事もあり、生前から死後の手続までを一括して受任していることもあります。
こうした複数の業務を兼任している場合はもちろん、死後事務受任者のみの業務であったとしても、死後事務委任契約の委任事項には、委任者(本人)の生前の債務の弁済(延滞家賃の清算等)や遺品整理等の家財整理が業務に含まれている事も多く、身寄りのない方が賃貸契約を結ぶ際の緊急連絡先としては適任者とも言えます。
また、死後事務受任者としても、死後事務に先立って見守り契約等を行う場合なら、契約者本人の異常にいちはやく気づけるきっかけにもなるため、緊急連絡先として登録しておいてもらえると、万が一の際に賃貸物件の管理会社との話(管理会社で保管している予備の鍵のでドアの開錠等)もスムーズに進むことになります。
委任者(本人)と死後事務受任者との契約内容によっては、賃貸物件における本人の生前の安否確認から万が一本人が死亡した際の遺品整理や物件の明け渡しについても、死後事務受任者にて対応が可能となるため、死後事務受任者を緊急連絡先として登録しておく意義は非常に高いものとなります。
もし、死後事務委任契約を結ばれている方で、賃貸契約における緊急連絡先で困っているような場合は死後事務受任者に「緊急連絡先」となってもらえるか確認のうえ、不動産会社にも死後事務受任者が緊急連絡先として登録できないか確認してみると良いのではないでしょうか。
遺品整理・死後事務委任のことは、名古屋の第八行政書士事務所までどうぞ~。