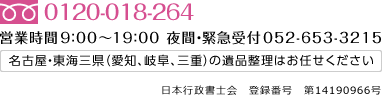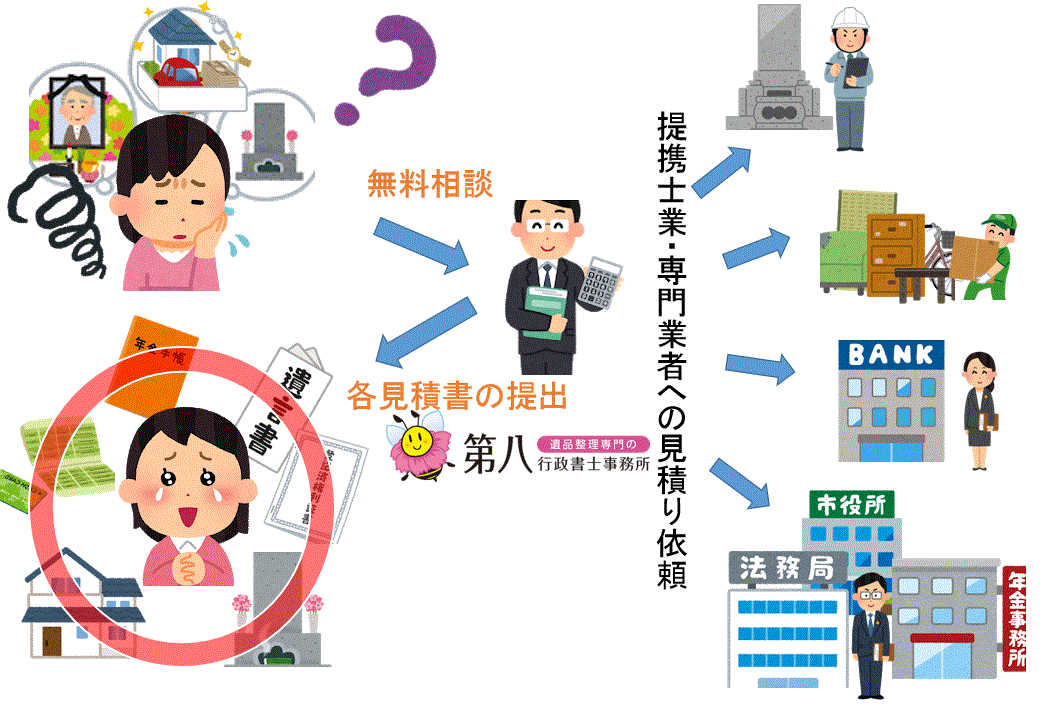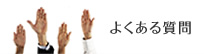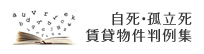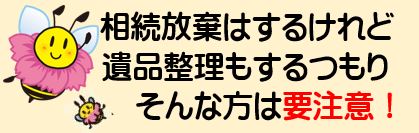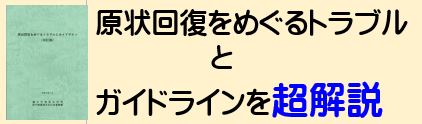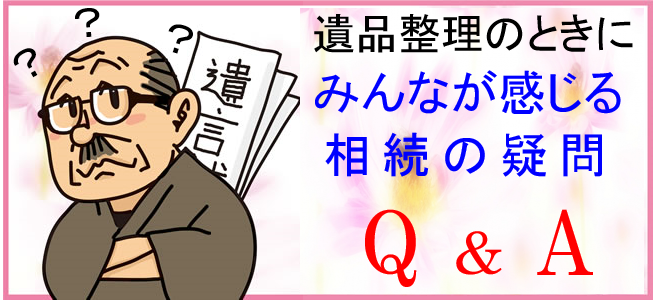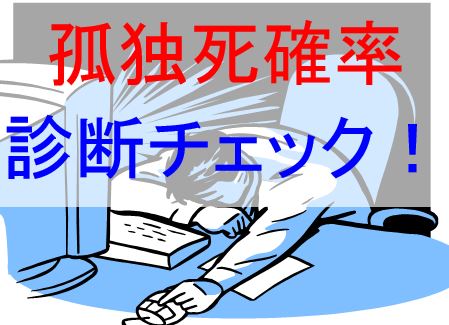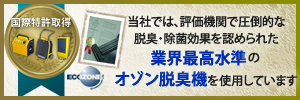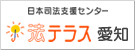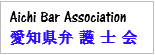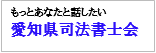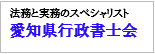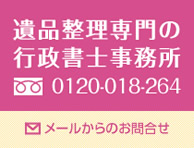名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2015.12.02
役場から紹介されて掛かってきた電話相談のお話し
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
空気が乾燥しているのか朝起きると喉がヒリヒリしています。皆さん風邪などひかれないようにご注意下さい。
さて、先週掛かってきた電話相談のお話し。ナンバーディスプレイで表示されている番号は県外の番号が表示されています。遺品整理や相続放棄などに関するご相談は全国から掛かってきますので、いつも通り電話に出てみると。
「あれ?これって個人でやってらしゃる行政書士事務所さんですか?」となんだか困惑された感じの相手方。こっちも???となりながらも「その通りですよ」とお答えしました。
なんでも役場に相談しに行ったら当事務所の電話番号を教えられて「一度ここに相談されてみたらどうですか」と言われたそうです。
その為、司法書士会や行政書士会などが行っている無料相談の受付窓口に繋がると思って電話してみたら個人の事務所に繋がってビックリしたという訳ですね。
さて、そんなこんなで繋がったご相談のお電話。相談内容は香典の取り扱いについてです。ご相談者の方の親族関係がいくぶん複雑なようで、香典を相続人で分割するのかしないのかで揉めてしまっているとのこと。
なんでも相続人のひとりが葬儀場とは別で預かった香典を喪主に渡さずに相続財産なのだから分割するべきだ!と主張して譲らないそうで、実際問題香典は誰が受け取るものなのかを教えて欲しいというご相談です。
まず、香典は相続財産か?
相続財産にはあたらないと考えられています。したがって、遺産分割の対象にもなりません。香典とは仏式等の葬儀で、死者の霊前等に供える金品を指します。弔問客が香典を贈る趣旨は、死者を供養しあるいは遺族の悲しみを慰めるという意味もありますが、その本来の意味として遺族らが葬儀費用などを出費することに対する負担を軽くする為に贈る相互扶助の精神がその根底にはあります。
ですので、この相互扶助の考えから行くなら、香典は故人に対して贈られたものではなく、その故人の為に葬儀をあげる遺族の負担を減らす為に贈られたものと考えられますので、原則「相続財産」には当たらないとされています。
では、実際のところ香典は誰が受取るべきものなのか?
香典は遺族の負担を減らすべく贈られていますので、葬儀を主宰する喪主に対して贈与されたものと考えられています。ですので、葬儀を終えた後に香典が余ったとしても喪主はそれを他の相続人に分配したり、相続財産に含めて考えたりする必要はないとされています。(その代わり香典だけでは葬儀費用が足りない場合は喪主の負担で支払うとする考え方もありますが)
したがって、一般的な解釈からいくと香典は喪主(葬儀の主宰者)に対する贈与とされています。過去の判例では次のようなものが出ています。
「香典は、被相続人の葬儀に関連する出費に充当する事を主たる目的として、葬儀の主宰者(喪主)になされた贈与の性質を有する金員であって、遺産には属さないと解される」
(東京家裁昭和44年5月10日)
ただ、一般的にはこのように考えられていますが、葬儀やそれを行った経緯(葬儀費用を喪主ではなく相続財産から支払ったなど)、また香典を渡された方の意思(故人のお子さんの為に使って欲しいと言って香典を渡されたなど)、地域の慣習(喪主とは別の主宰者もいる地域慣習など)で考え方が変わる可能性もありますのでご注意ください。
![]() ←ブログの内容が面白ければ1clickして頂けると励みになります!
←ブログの内容が面白ければ1clickして頂けると励みになります!
にほんブログ村
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や相続相談・賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くだいさいね。![]()