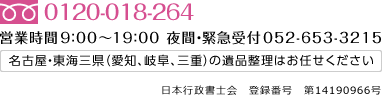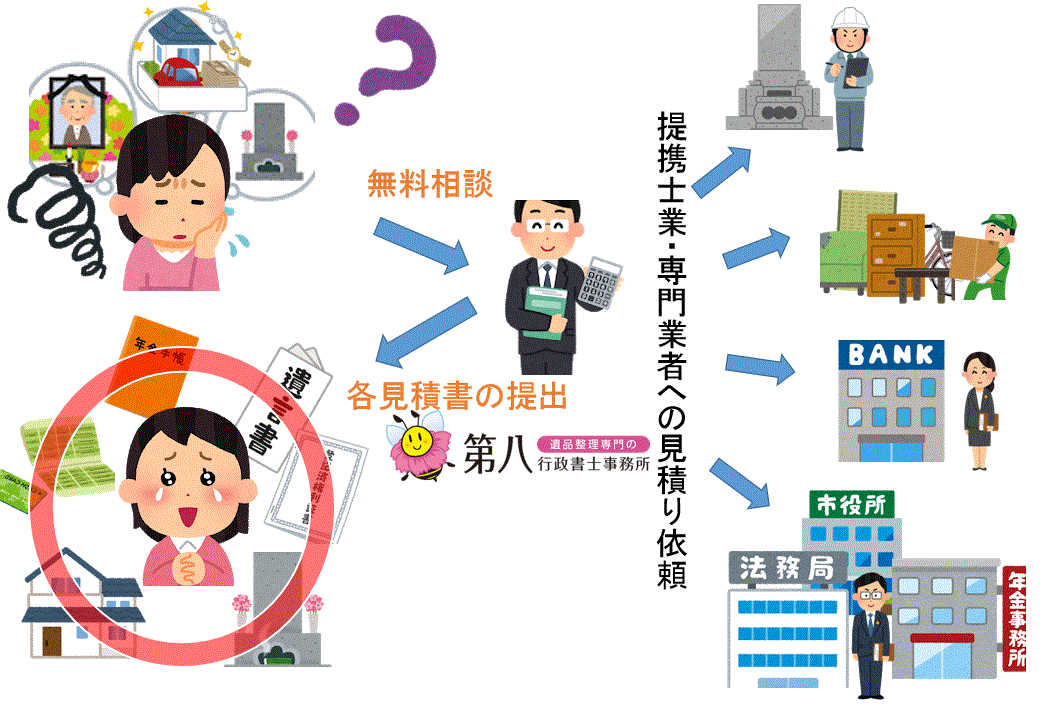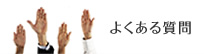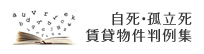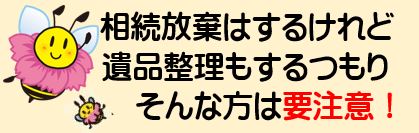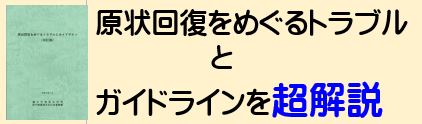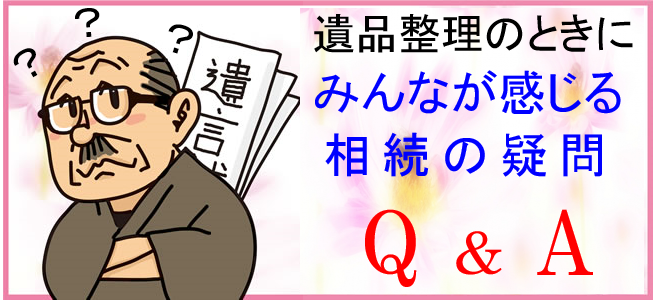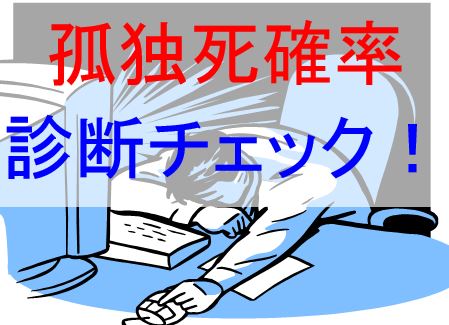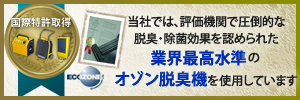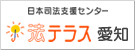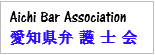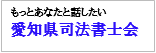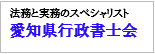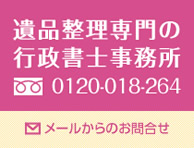名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ
2017.05.30
死後事務委任契約とは
おはようございます。名古屋の遺品整理・特殊清掃専門第八行政書士事務所の谷です。
暑いですね~ 名古屋も真夏日を越える日が出てきて、仕事着も背広から半袖、ネクタイ無しのクールビズ仕様へと変更です。(ま~、背広より作業着を着てることの方が多いのですが、、、、)
名古屋も真夏日を越える日が出てきて、仕事着も背広から半袖、ネクタイ無しのクールビズ仕様へと変更です。(ま~、背広より作業着を着てることの方が多いのですが、、、、)
熱中症の危険が高くなってきています。暑さに慣れていない体で無理な運動などするとすぐにバタンキュ~してしまいますのでお気をつけくださいね。
さてさて、遺品整理をしているとこんな場面に出くわすことがあります。成年後見をされている弁護士の先生からのご依頼で、被成年後見人(弁護士などの成年後見人が付いている高齢者の方など)だった方の遺品整理をしているとご自宅から多額の現金や通帳が見つかるといった場面。
その他にも有価証券や貴金属類など金銭的価値のある物が見つかることも多いのですが、それらは依頼者である弁護士の先生へとお渡しします。これらの貴重品の行方ってどうなると思われますか?
もちろん相続人の方がいらっしゃれば、成年後見終了後に弁護士の先生の清算業務の後に相続人へと渡されることとなるのですが、成年後見人が付されている方の中には相続人がいないということも珍しくはありません。
だって、面倒を見てくれる親族がいない、いても疎遠になっていたり、近にくいなくて迅速な手続きが取れないといった事情があったりするからこそ第三者である弁護士などの成年後見人が付いているということなのですから。
つまり、成年後見制度を利用されていた方の遺品整理では見つかった貴重品類を受け取るべき相続人がいないということも珍しくはないということです。
では、発見された多額の現金などは誰が受け取るのでしょう?弁護士の先生の報酬になったりするの?それとも遺失物のように最終的には発見者である遺品整理業者の物になるの?もちろんそんな訳はありません。
相続人がいない方の相続財産は法律で定められた相続人調査や広告期間などを経た後に最終的には国庫へと入ることになります。簡単に言えば、誰も受取人がいなければ国が持っていってしまうということですね。
確かに誰も受取人がいないのなら最終的に国へと行ってしまうのは仕方の無いことかもしれません。でも、生きている時は税金をしっかり払っているのに死んだ後もコツコツ貯めた貯蓄を国が持っていってしまうとなるとなんだか釈然としないものを感じる方も多いのではないでしょうか。
どうせ、国が持っていってしまうのならもっと有効な使い方がしたかった!そう考えていたとしても死んでしまってからでは草葉の陰で泣くしかありません。せめて、自分の代わりに自分の遺した財産を自分の思っていたように活用してくれる人がいたならば!!
そう考えてしまいますよね。これについても方法が無い訳ではありません。まず、一般的なところで言えば「遺言書」ですね。自分の財産をどのように分けたいかの意思表示をする書面であり、相続の場面ではおなじみのものとなります。
ドラマなどでも「遺言が出てきた!」「その遺言書は偽者だ!」と遺言書は相続における題材としては最もポピュラーなものとなっています。
しかし、誤解されがちですが遺言書にはなんでも書けるわけではありません。もっと厳密に言うのなら、書いてもいいけれど法律的効果が発生する事柄と発生しない事柄があるということです。
遺言書の効果は主に相続および財産の分け方を示すものであり、その他の遺言書に記載して法律的な効果が及ぶものは法律で定められています。つまり、なんでもかんでも遺言書に記載しておけば全てその通りに実現されるという訳ではないということです。
次に最近話題になってきている「家族信託」。これは古くからある遺言の制度とは全くの反対でここ数年で取り上げられている相続の方法のひとつです。遺言書と異なるのは自分の財産を自分の思うように利用でき、また何世代にも渡った財産運用が可能となるというものです。
ただ、制度としての歴史が極端に浅く、遺留分の問題や銀行側の対応などでかなりハードルが高く、実際にプランを作成できる専門家も少ないということで実際に利用するにはまだまだ一般的とはなっていません。「これは使える!」と思って飛びつた士業の中では既に依頼者側と訴訟になっているものもあるようで、もう少し制度的な熟成が待たれるのではと思っています。
最後に今回のメインでもある「死後事務委任契約」です。あまり聞かない言葉だと思います。市役所などに問い合わせても「なんですか、それ?」と言われてしまうことがあるくらいの制度でもあります。
ただ、今後の少子化、超高齢社会では必須ともいえる制度であり、今後利用される方が増えてくると思われる制度のひとつでもあります。では実際「死後事務委任」とは何か?というと。
まずは、読んで字の如く、「死後」の「事務」を「委任」する制度となります。委任制度、わかりやすい例えで言うなら先ほど話題になった成年後見制度を例に話していきます。
成年後見制度は認知症の方などの法律行為(施設入所の手続きや支払いなど)を手助けする、成年後見人が被成年後見人をサポートする制度ですよね。
ですが、一般的な委任契約と同様にその制度は本人(被成年後見人)の死亡で終了してしまうというのが問題のひとつとしてあります。簡単に言うなら本人が死亡したら弁護士などの専門家の職務としてはそこで終了。後は残った財産などの清算業務を行って報告すれば終わりということです。
何が問題なの?となるかもしれませんが、本人の死亡と同時に職務が終了となるということは、専門家などが行う成年後見では葬儀や埋葬、遺品整理、賃貸物件の明け渡しなどはその職務には含まれていないということです。
つまり、本人が死亡した以上は成年後見も終了していますので後は知りませんとなってしまう可能性があるということですね。
でも、そんな中途半端では賃貸の大家さんや施設関係者は困りますし、亡くなったご本人だってそんな迷惑を掛けるつもりは無かった!となってしまいますよね。
そういった際の問題を解決するのが「死後事務委任契約」となるわけです。前述のように「死後」(本人が亡くなった後)の「事務」(葬儀や埋葬、遺品整理など)を「委任」(本人に代わって契約や解約などの手続きを第三者に行ってもらう)する制度となります。
この死後事務委任契約は任意後見契約などではセットで結ばれることが多いですが、この死後事務委任契約を結ぶことで、生前に自分の葬儀や埋葬の仕方、誰に連絡をして、どういった手続きをお願いするといった遺言書では書けない、書いても法律的な効果を発生させられない事柄を第三者に委任することができます。
遺言書と違って死後事務委任契約は委任契約であり、契約は委任者(本人)と受任者(専門家など)の同意のもとで行われますので、契約が成立した以上は受任者は勝ってに契約内容を破棄することができず、死後事務委任契約で定めた内容を実現していく必要があります。
ですので、生前に家族へ口頭で伝えた「お願い」やエンディングノートなどに記載した「死後の希望」、そして遺言書に記載した法律的効果の発生しない「付言事項」とは異なった契約に基づく義務が受任者に発生しますので、本人の希望がより実現されることとなるという訳ですね。
この死後事務委任契約を遺言書と組み合わせて利用することによって、最初に述べた「財産が国庫へ!」といった事態や「自分の死後、誰が葬儀をあげてくれるのだろう?」といった不安を解消することができることになります。
まだまだ、一般的と言える制度ではありませんが、身寄りが無い、または家族はいても高齢の兄妹には無理をさせたくないといった事情や疎遠な家族の世話にはなりたくないといった事情が今後の日本では多くなってくると予想される中、制度に詳しい専門家の需要は伸びてくるのではないでしょうか。
第八行政書士事務所では遺品整理や生前整理の経験を活かし、また相続の専門家として他士業とも連携して「死後事務委任契約」の利用を推進しています。もし、ご自身の死後の事で不安がございましたらご相談くださいね。
詳しくは「死後事務委任契約について」をご確認ください。
名古屋の遺品整理・特殊清掃専門 第八行政書士事務所 代表 谷 茂
第八行政書士事務所は名古屋を中心に東京、大阪など全国で遺品整理・特殊清掃のご相談を受け付けております。
その他の地域にお住まいの方でも遺品整理や生前整理、相続相談、賃貸トラブルなどのご相談は随時お受け致しておりますのでお気軽にご相談くださいね。![]()